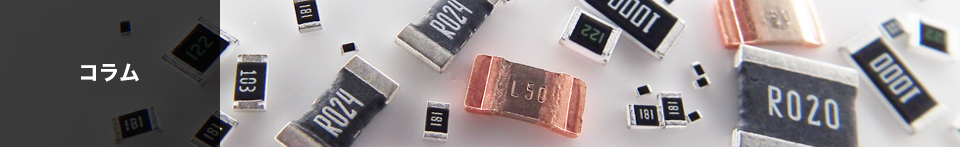
抵抗器の故障モードの一つに“断線/オープン”がありますが、その原因のひとつに
「電蝕」があります。電蝕で抵抗器が断線した場合、時に電子機器が停止する
重大な不具合が発生します。電蝕は高湿度や腐食性環境で発生しやすい現象ですが、
このような環境下でも電蝕を発生させない対策として弊社がお勧めしている
メタルグレーズ皮膜を用いた抵抗器の特長を説明します。
また、電蝕加速実験の結果と、そこから考察した寿命を紹介します。
メタルグレーズ皮膜製品
耐電蝕抵抗器 AECシリーズ
耐サージ抵抗器 ASR/ASRMシリーズ
厚膜チップ抵抗器 CRシリーズ
耐硫化厚膜チップ抵抗器 CRAシリーズ
耐サージ厚膜チップ抵抗器 CRSシリーズ
→アプリケーション
電源、UPS、半導体製造装置、FA機器、車載、照明、家電全般
部品としての構造は一般的な抵抗と変わりありませんが図1、表1に示すように導電層
(皮膜)部分の構造が一般抵抗と異なり耐電蝕・腐食性に有利になっています。
一般的な薄膜抵抗 メタルグレーズ皮膜抵抗
図1 抵抗器における導電層の構造図
表1 導電層構造比較
| 一般(薄膜)抵抗 | メタルグレーズ抵抗 | |||
| 導電物質 | カーボン、ニッケルクロムなど | – | 酸化ルテニウム | – |
| 導電層構造 | 導電物質自体が導電層を形成 | – | 導電物質が拡散したホウケイ酸ガラス層 | – |
| 導電層厚 |
0.1um~数µm |
△ | 10µm前後(一定) | 〇 |
| 耐電蝕性 | 環境により電蝕(故障)発生することがある | △ |
原理上、電蝕は発生しない |
◎ |
ポイントは下記2点です。
(1)導電物質が酸化ルテニウムであること
市場での抵抗器の電蝕故障はほとんどがカーボン抵抗におけるものであり
そのメカニズムは、導電物質である炭素(C)と、水の電気分解により発生
したOH-イオンが化学反応し、CO2(ガス)化してしまうことで導電性
がなくなる(抵抗値高化、断線)というものです。
メタルグレーズ皮膜は導電性を担う物質が酸化ルテニウム(RuO2)であり、
上記の電蝕メカニズムが当てはまりません。
(2)導電物質がガラスで保護されていること
導電物質がカーボンではないとはいえ、導電層が酸化ルテニウムだけからなる
状態であれば、別のメカニズム、例えばイオンマイグレーション(→Wikipedia)
により故障する可能性があります。
しかしながらメタルグレーズ皮膜は導電層全体がガラス(ホウケイ酸ガラス)
主体でできており、いわば導電物質がガラスで保護された構造となっています。
ガラスは耐食性に優れることから様々な分野で利用されいるのは周知のとおり
ですが、その中でもホウケイ酸ガラスは一般ガラスより耐熱性、ハロゲン・水・
中性・酸性溶液に対する耐食性が高いことから光学部品、理化学機器、医療器具、
温度計などに利用されています。イメージしやすい例としては化学の実験で使わ
れる試薬が入ったあの茶色いビンやビーカー、フラスコなどです。
それらと同じ構造を持つメタルグレーズ皮膜は耐腐食性において抵抗器中最強と
いえます。
一般抵抗と比べ価格は高めになりますが、それ以上のコストパフォーマンス
(信頼性、耐久性)をお約束します。
参考
|
ガラスは万能ではなくフッ化水素(HF)やアルカリなどの限られた物質で腐食します。 ガラス工芸などではこの性質を利用してフッ化水素が多用されています。 抵抗器が使用される自然界や電気機器内にフッ化水素が存在することはまずありませんし、また、アルカリによる腐食速度は常温では非常に遅く、表面がすりガラスのようになる程度と言われていますので、抵抗器での影響も極めて小さいと考えられます。 |
◎実験内容
抵抗器を水道水およびリン酸水溶液に浸した状態で通電し抵抗値の変化で耐電蝕性を評価する。
◎サンプル・条件
耐電蝕抵抗器(AECシリーズ)と汎用カーボン抵抗器の比較で行う。詳細は下記。
サンプルは導電層の露出した状態(皮膜保護/外装コーティングのないもの)を用いる。
n=各10
◎実験結果
カーボン抵抗:
試験開始後、20秒以内に全数OPEN断線となった。特にリン酸溶液下では数秒で断線。
メタグレーズ抵抗:
300秒後でも抵抗値変化率は 10%未満であった。
リン酸溶液下ではリード線が腐食で切れ試験中止したが抵抗皮膜へのダメージは軽微。
抵抗値変化の様子を図3に示します。 (n=10各々の抵抗値変化をプロットしてある)
図3 時間-抵抗値変化率グラフ(注:①②と③④は時間スケールが異なる)
試験後のサンプル写真
◎考察: 今回の試験は市場において何時間に相当するか?
通常は市販状態の製品(皮膜保護、外装コーティング有り)で評価を行うため
今回の条件においては検証が難しいのですが、弊社で過去にカーボン抵抗
(市販状態)を用いて行った電蝕加速試験のデータベースと単純に照合して計算
した結果、水道水条件下で5秒あたり100年以上に相当するという驚きの結果に
なりました。(抵抗値変化率+20%=寿命と仮定)
仮に5秒=100年とすると、メタルグレーズの300秒は、100年x300秒/5秒
=6,000年に相当するという計算です!!
更に、水道水とリン酸溶液の抵抗値変化の度合いを比較すると後者は約10倍の
変化と見積もることができるので、リン酸溶液のメタルグレーズ抵抗は
6,000年x10x(240秒/300秒)=48,000年に相当!!!
何だか分からない数字ですが、電子機器内環境でリード線が腐食(風化?)して切れる
には相当な時間が必要なことは間違いないのであながちでたらめな数字ではなさそうな
気がしませんか?
最後に強調しておきたいのは、48,000年はリード線の寿命であってメタルグレーズ皮膜は
それ以上の耐久性であることが今回の実験から推測されるということです。
メタルグレーズ皮膜製品
耐電蝕抵抗器 AECシリーズ
耐サージ抵抗器 ASR/ASRMシリーズ
厚膜チップ抵抗器 CRシリーズ
耐硫化厚膜チップ抵抗器 CRAシリーズ
耐サージ厚膜チップ抵抗器 CRSシリーズ
→アプリケーション
電源、UPS、半導体製造装置、FA機器、車載、照明、家電全般
関連コラム