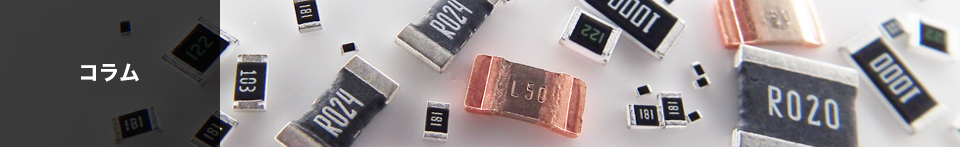
◆高抵抗測定時の注意点
✔ 導体(人間含む)を近づけない
✔ 測定中の治具(クリップ)に触らない
✔ 振動を避ける
✔ 静電シールドを施す
抵抗の測定には、一般的にデジタルマルチメータや抵抗計が使用されます。測定原理は、
コラム「低抵抗の測定方法と取扱い注意事項」で書きましたので、ここでは高抵抗を測定
する際の実践的な注意点を示しました。
◆高抵抗測定時なぜ抵抗値が安定しないのか?
デジタルマルチメータや抵抗計の高抵抗レンジの測定電流はμAやnAオーダーの微小電流
です。その為、“外来ノイズ”や“漏れ電流”が測定系に影響を及ぼし誤差の原因になります。
外来ノイズは“静電結合”や“電磁誘導”という物理現象として影響を及ぼします。
◇静電結合とは?
抵抗測定における静電結合は測定ケーブルの近くに導体がある場合にケーブルと導体間
で浮遊容量を持ち、起電力が発生する現象です。人間も導体ですので測定者が測定系に
近づいたり、離れたりすると浮遊容量が変化するため測定値がばらつきます。
◇電磁誘導とは?
空間の磁界が導線(測定ケーブルや測定器内の回路)に作用して、起電力及び電流を発生
させます。フレミングの左手の法則でお馴染みの現象です。
◇漏れ電流とは?
本来絶縁されているはずの場所、経路で流れる微小電流です。計測器が流す測定電流の
全てが測定物に流れるのが理想ですが、漏れ電流として分流してしまうことで誤差要因
となります。普段絶縁物として扱っているプラスチック・樹脂材料も109-1015(Ω・cm)
の抵抗があり僅かに電流を流します。また人体も導体です。測定物が高抵抗で測定電流
が小さくなるほど漏れ電流の影響が大きくなります。
漏れ電流の例: 手を通じて微小電流(赤矢印)が流れる
◆測定誤差、ばらつきを低減するには
抵抗測定時の注意事項は計測器メーカーのサイトなどで詳しく解説されていますが、
簡単な対策として冒頭で挙げた点に気を付けるだけで誤差要因を低減して改善される
ケースもありますので試してみては如何でしょうか。
・導体(人間含む)を近づけない = 静電結合防止
・測定中の治具(クリップ)に触らない = 漏れ電流防止
・振動を避ける = 電磁誘導防止
・静電シールド・アースを施す = 静電結合・電磁誘導防止
シールドの例: 測定時には完全に蓋をしてアースへ接続します
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
→定格・抵抗値から素早く製品を検索するにはこちら